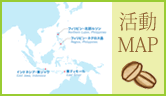エコシュリンプの産地であるインドネシアの東ジャワ州シドアルジョ県において、APLAのパートナー団体であるKOINが地域住民や行政と協力しながら構築、発展させてきた家庭ごみ回収活動は、すっかり地域社会に根を張り、他地域からの視察なども多数受け入れるようになっています。
そんななか、同じエコシュリンプの産地である南スラウェシ州ピンラン県でも持続可能な家庭ごみの管理システムを構築できるように、先進事例から学ぶ機会をつくろう、という話になり、2025年4月末に同県マッティロ・ソンペ郡マットンボン村のムハンマド・タヒル村長およびランリサン郡ランリサン区のフィルマン区長の二人を東ジャワ州に招聘しました。
二人は、エコシュリンプの産地でありKOINが活動立ち上げを支援したシドアルジョ県カランガニャル村とスダティ・グデ村、加えて、隣接するスラバヤ市のジャンバンガン区のリサイクルセンターの3カ所を見学し、それぞれ異なる管理システムを学ぶ機会を得ました。
ソポニョンコ3Rごみ処理施設(カランガニャル村)
このごみ処理施設は、村長の管轄する地域住民組織(KSM)によって運営されています。ここで二人は、ステークホルダーおよび村政府の積極的な参加のもと、「リデュース・リユース・リサイクル(3R)」のシステムが安定して実施されている様子を学びました。
特に注目すべき点は、地域の自治会および村の行政の参画により、カランガニャル村のすべての住民がごみ管理プログラムに参加することを義務づける村の条例が制定されていることです。これにより、ごみ処理の意識が地域全体に浸透しました。ごみの収集は定期的に行われ、リサイクルされたごみは販売され、収益となっています。中規模なごみ処理施設で、運営方法もシンプルで初心者にも模倣しやすいモデルです。また、ごみ処理から収益を生み出すという点で、革新的な取り組みがなされています。
村落事業体3R ごみ処理施設(スダティ・グデ村)
このごみ処理施設は、村落事業体によって直接運営されており、村の行政、地域住民、そして村の事業グループとの間で良好な相乗効果が生み出されています。
プラスチックごみは収集・分別され、プラスチック加工業者に販売されます。一方、有機ごみは堆肥や液体肥料に加工され、住民の畑で再利用されています。このビジネスモデルは、住民に追加収入をもたらし、村の経済強化につながっています。 大規模なごみ処理施設はで、1,000 世帯以上を対象に運営されており、約40 人の作業員が雇用されています。
ジャンバンガン・リサイクルセンター(スラバヤ市)
ジャンバンガン区のリサイクルセンターは、スラバヤ市政府の管理下にあり、市の予算による資金提供と効率的な物流システムにより、大規模なごみ管理体制が整っています。
ごみの分別は住民グループによって各家庭で行われ、その後ごみ処理施設で管理されています。処理された資源は市場や工場へと流通され、有機ごみは堆肥などに加工されます。特に注目すべき点は、データ管理と記録のシステムです。これは、村レベルでの透明性と説明責任を確保するための規範となるからです。
今回の一連の研修を通じて、二人の参加者は、地域住民および各自治体が真剣かつ根気強く組織的なごみ管理に取り組んでいる姿勢に深い感銘を受けた、と言います。 タヒル氏は、「3R の概念は単なるスローガンではなく、地域社会の日常的な習慣として実践されている」と述べ、「ごみ管理の成功は、設備や施設だけでなく、住民の意識と協力にかかっています。これこそが私たちがマットンボン村で築きたいものです」と言葉を続けました。フィルマン氏は、ランリサン区でも今回学んだごみ管理のコンセプトを地域の地理的・社会的条件に合わせて導入したいと述べました。区における予算の使用には、村とは違い県知事の許可が必要であるため、ごみ管理のための予算について郡長および県知事と協議する予定であると話しています。
今回の研修は、単なる学びの旅ではなく、変革の出発点となるものでした。この学びの成果が、持続可能なごみ管理を通じたより清潔で自立した豊かな地域社会を築くための道をピンラン県の村々に切り開くことを強く願っています。
報告:ヘンドラ・グナワン(KOIN)
翻訳:松村多悠子(まつむら・たゆこ/APLA事務局)
こうした学びの機会の創出やエコシュリンプ産地での環境保全活動は、皆さんからのご支援で実施することができています。ぜひご支援をお願いいたします。ご支援お申し込みフォームから「14. 今回のみの寄付(インドネシア)」をお選びいただき、必要事項をご入力願います。クレジットカード決済か銀行振り込みがお選びいただけます。









![チョコラ デ パプア ビター(タブレット)100g[1017円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/cco_01b_tablet100.png)
![チョコラ デ パプア オーレ(タブレット)100g[935円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/cco_01_tablet100.png)
![みんなでつくるコーヒー豆チョコレート(20袋入り)【送料無料/倉庫直送】[14097円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/coffeebeans_choco3.png)
![みんなでつくるコーヒー豆チョコレート[742円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/coffeebeans_choco1.png)
![チョコラ デ パプア マスコバド糖チョコレート(20袋入り)【送料無料/倉庫直送】[14836円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/msc_choco20.png)
![チョコラ デ パプア マスコバド糖チョコレート[781円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/msc_choco2.png)
![パプアのカカオ豆 《作りかた付》[894円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/cco_beans2.jpg)
![パプアのココアパウダー(20袋入り)【送料無料/倉庫直送】[18160円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/ccopow2box.png)
![パプアのココアパウダー[956円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/ccopow2.png)
![パプアのカカオニブ[1256円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/cco_nib2.jpg)
![パプアのカカオニブ(20袋入り)【送料無料/倉庫直送】[23865円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/cco_nib_box2.jpg)
![『パプア・チョコレートの挑戦』 【クリックポスト可】[660円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/b_atjapla_03.jpg)
![クラフトチョコレート カカオキタパプア カカオ67%[981円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/craft67.png)
![坂本千明さん「アイーダ」缶バッチ 【クリックポスト可】[300円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/Aida300.jpg)
![旅するシェフと作った!ぽこぽこバナナカレー (4パック入り)【送料込み】[2020円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/bnn_pococurry1.jpg)
![絵本『バナナのらんとごん』 【クリックポスト可】[2750円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/rangon_b.png)